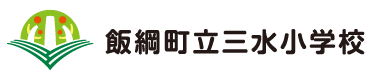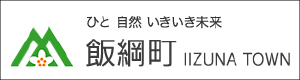今年に入って、全国各地で、また、長野県でもクマ出没に関して、多くの報道がされています。昨年度は、ここ三水でも、クマの目撃情報がありました。そこで、万が一のために、本日クマ授業を実施しました。地域の方々に、クマ出没に関してお話をお聞きすると「昔からクマは出てきているよ」等のお話をいただきました。この三水もクマと共存してきた地域であるように思います。ただ、このところの報道を目にすると、クマ対策への意識を高めることは、子どもたちにとっても重要だと考え、今回のクマ授業を実施することにしました。
講師の先生は、NPO法人信州ツキノワグマ研究会対策員の方です。長野県各地の小学校でクマ授業を行っている方です。この授業で、子どもたちは、クマの生態やクマに襲われないようにするための方法等を知ることができました。クマに関して大いに学ぶことができたものと思います。以下、教えていただいたことを端的に載せさせていただきます。
【クマについて教えていただいたこと】
1 クマは、遠くは見えないが、小さな音はよく聞こえるし、遠くのにおいもよくわかる。
2 クマは、夏はやせていて、秋は太る。雑食性…季節によって食べ物が変わる。(春…やわらかい草や新芽、花等。夏…草や木の実、アリ、ハチ等。秋…ドングリやクリ、クルミ等。冬…食べない。)
3 夏は、食べ物が一番少ない季節 → 今の時期は食べ物を探して歩きまわる。(秋もドングリを探しまわる)
4 クマは、春と夏は、夜休むことが多い。ただし、畑の近くでは、夜に活動する。秋は、昼も夜も食べ物探し。
5 クマは、一生のほとんどの時間をひとりで過ごす。季節によって、生活するところや休むところも変わる。
6 めったに人を襲うことはない。近くでバッタリ出会うと襲うことがある。(自分や子どもを守るために襲う)
7 襲われないためには…音を出す。人がいることをクマに教える。
8 林ややぶに一人で入らない。ごみをしっかり片づける。
9 クマに出会ってやってはいけないこと → ①大声を出す ②物を投げる ③走る ④戦う ⑤驚かす
10 クマに出会ってしまったら → ①落ち着く ②ゆっくり後ずさりをする
11 クマに出会わないようにすることが大切
クマにバッタリ出会わないようにすることが最善策です。そのためには、音を出して自分の存在をクマに分からせるようにすることが大切です。今後もクマに出会わないよう、クマよけ鈴の装着等、学校でもご家庭でも、正しい対応をしていければと思います。
【クマ授業の様子】